本日のWeb配信について
Web参加の皆様
本日は配信上の不具合が発生し、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
講演の完全版映像を後日提供させていただきます。
お申込みいただいたアドレスに改めてご案内メールを送信させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
お陰様で無事盛会のうちに終了することができました。

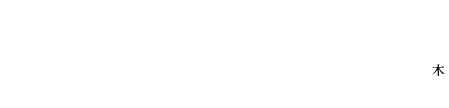
Web同時開催CPD・CPDs認定プログラム
たくさんのご参加ありがとうございました
本日のWeb配信について
Web参加の皆様
本日は配信上の不具合が発生し、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
講演の完全版映像を後日提供させていただきます。
お申込みいただいたアドレスに改めてご案内メールを送信させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
土サミット2022参加者の皆さまにアンケートをお願いしております。
※アンケートの受付は終了致しました。
『土サミット2022』現地見学会
集合時間変更のご案内
現地見学会について、バスの出発時間に変更がございますので、ご案内させていただきます。
同内容をご参加の皆様にメール送信しておりますので、ご確認の程宜しくお願い致します。
2号車の出発時間について
12:40出発予定でしたが、見学地周辺の交通状況を鑑みて、出発時間を早めることになりました。
出発時間が10分早まり、12:30発ホテルニューオータニ東京となります。
(1号車は予定時間通り13:00発です)
タイトな時間設定となっておりますので、時間厳守で進めてゆきたいと思っております。
皆様のご協力の程、どうぞよろしくお願い致します。
※見学会は大型バス2台(1号車・2号車)となります。工程がバス毎に異なるため、集合時間に
ご注意くださいますようお願い申し上げます。(行程資料添付)集合時間に関しましては、下記の通り
となります。
また、現地見学会後に懇親会も予定しております。ご希望の場合は前日までにご連絡ください。
◇◆◇ 土サミット2022 ◇◆◇
プラント現地見学会
日 付:10月20日(木)
出発時間:1号車 13:00 ・ 2号車 12:30
受付集合場所:ホテルニューオータニ東京
「宴会場階の正面玄関内入口付近」※バスも同じ階場から出発します。
~見学会スケジュール~
【第1班(1号車)】
12:00~ 受付
12:50 集合
13:00 ホテルニューオータニ東京 バス出発
13:20 東京都建設発生土再利用センター
15:10 成友興業株式会社 城南島第二工場
17:10 ホテルニューオータニ東京 バス到着
【第2班(号車)】
12:20 集合
12:30 ホテルニューオータニ東京 バス出発
13:10 成友興業株式会社 城南島第二工場
15:00 東京都建設発生土再利用センター
17:00 ホテルニューオータニ東京 バス到着
※お願い・注意事項について
・バスの乗車時及び現地見学中はマスクの着用をお願いします。
・受付時に体温確認をさせていただきます。
・移動中のバスの中では大声での会話を禁止とさせていただきます。
・雨天等の場合は、屋内の設備等の見学のみになることをご了承ください。
※服装について
・作業着等の必要性はございません。
再利用センター場内(屋外)見学はマイクロバスでのご案内となります。
移動は舗装されたところのみとなりましたので。汚れる心配はございません。
◇◇懇親会のお知らせ◇◇
現地見学会後、参加者による懇親会を予定しておりますのでご案内致します。
日時:10月20日(木)17:30~19:00
(バスの到着時間により変更となる場合がございます)
場所: ホテルニューオータニ ガンシップ
会費:6,300円/名 (お申込み締切19日12:00迄)
※お申し込みは、メール又はお電話にて事務局にご連絡ください。
e-mail: info@tsuchi-summit.com
土サミット2022
開催日:2022年10月21日(金)10:00~17:30
会 場: ホテルニューオータニ東京
東京都千代田区紀尾井町4-1
アクセス: https://www.newotani.co.jp/tokyo/access/
*土サミット詳細につきましてはHPをご覧ください
土サミット2022: https://tsuchi-summit.com/
土サミット2022は ~CPD・CPDS認定プログラムとなっております~
●CPD >単位:6.5(来場・Web対応)
●CPDS>単位:7(来場のみ対応)
<受講証明発行を希望される方>
(1)ご来場の方
当日、土サミット閉会後、受付にて受講証明をお渡しいたします。
CPD・CPDS双方の受講証明書を会場にて発行させていただきます。
(2)Web参加の方
― CPD受講証明書:下記の要綱によりメールにてお送りします ―
当HPより「受講証明発行用・感想用紙」をダウンロードのうえご記入いただき、メールにて土サミット事務局(info@tsuchi-summit.com)へお送りください。
受講証明発行用・感想用紙 回答期日:2022年10月21日(金)~2022年10月28日(金)17:00まで
※回答期日を過ぎますと受付いたしませんので、ご注意ください。
- CPDS受講証明書は対応しておりません -
おかげさまで、現地見学会は定員となりましたので受付を終了させていただきます。
ありがとうございました。
お申込みいただきました皆様へ
当日は、「宴会場階の正面玄関」にて受付を致します。
10月20日(木)受付開始時間;12:40~
※バスも宴会場階の正面玄関より出発します。
※お申込みいただきました皆様には改めてご連絡させていただきます。
◇◇懇親会のお知らせ◇◇
現地見学会後、懇親会を予定しております。
ご希望の方は、事務局までお申し込み下さい。
会費は当日いただきます。
日時:10月20日(木)18:30~20:00
(バスの到着時間により変更となる場合がございます)
場所:ホテルニューオータニ ガンシップ
https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/gunship/
会費:6,300円/名
連絡先:土サミット事務局 担当・宮澤
info@tsuchi-summit.com
TEL 03-3526-2129/FAX 03-3526-2139
公益社団法人 地盤工学会 関東支部 様より土サミットTOKYO2022の後援を頂きました。
公益社団法人土木学会様より土サミットTOKYO2022の後援を頂きました。
土サミットTOKYO2022の特設サイトでは参加お申し込みを受付中です。
また、オフィシャルサポーター・オフィシャルスポンサーの募集要項についても公開しております。
土サミットは土に携わる各業界の皆様を取り巻く問題、今後の課題を話し合い、各業界団体の垣根を超えた情報交換の場として開催しております。
土のリサイクルを通して自然の財産を守る私達の業界について、多くの人に知っていただける場になれば幸いです。
昨年度発生した、大規模な土石流災害を受け、建設発生土をはじめ土の問題がクローズアップされております。土のリサイクルの現状と災害時の土について、各機関からの講演とパネルディスカッションにて考えてみたいと思います。
生命の生育媒体のひとつである「土」は、多くの浄化作用を通して私達に恩恵をたらしております。
自然のままで残せる土を出来るだけ多く次の世代へ残す。
今年は、パネルディスカッションと学生ワークショップにて、土の未来を見つめ、土の将来を語ってもらいます。
今年の土サミットのテーマは「災害と土」
昨年度の大規模土石流災害により、危険な盛土に対する規制等、建設発生土の取り扱いが大きく見直され、土の様々な問題が取り沙汰されるようになりました。
今年は、第一部「災害と土」と題し特別講演・災害対策事業等を紹介。第二部に「建設発生土施策講演」、第三部に自治体等における建設発生土等への取組の講演とオンライン見学も取り入れました。
第四部の「学生ワークショップ」にて未来を担う世代の声を聴き、最終の第五部「パネルディスカッション」では、第一部から第四部の議論を踏まえ、~災害と土の先へ~土の未来をさぐる~と題して、過去から現在そして未来を見つめ議論を展開します。
「土」の問題が注目を集めている今、改めて土の持つ本来の役割・将来性を発信していきたいと考えております。
また、昨年のアンケートに基づき、ご希望の多かったプラント現地見学会も前日(20日)に開催致します。
土サミットは、皆様の声をもとに知りたい情報を発信し、業界団体の垣根を超えた会として、業界の輪を広げて行きたいと考えております。
今年も 土の未来を拓く対話の会に是非ご参加ください。
主催者代表
一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会
理事長 赤坂 泰子
主催者挨拶
一般社団法人 全国建設発生土リサイクル協会 理事長 赤坂 泰子
来賓挨拶
国土交通省大臣官房 技術審議官 佐藤 寿延
一般社団法人 先端建設技術センター 理事長 佐藤 直良
特別講演
「災害と土、そして、自然由来重金属等含有土への対応(仮)」
京都大学大学院 地球環境 学堂長 教授 勝見 武
「東日本大震災からの復旧・復興事業における建設発生土等の活用事例」
宮城県 農政部 農村防災対策室 技術補佐 佐山 雅史
「レジリエントなまちづくりを支える建設泥土高度再資源化施設の紹介」
~都内における建設泥土・災害廃棄物再資源化対応と将来展望~
成友興業株式会社 代表取締役 細沼 順人
「東京都における土砂災害の災害廃棄物処理の対応」
東京都 環境局 資源循環推進部 資源循環計画担当課長 荒井和誠
「富士山と災害と「土」について」
国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 事務所長 藤平 大
昼食休憩
基調講演
「建設発生土の有効利用について」
国土交通省総合政策局 公共事業企画調整課
インフラ情報・環境企画調整官 隅蔵 雄一郎
「建設発生土の官民有効利用マッチングシステムについて」
一般財団法人 先端建設技術センター 技術調査部 グループリーダー松橋 宏明
「東京都における建設発生土対策について」
東京都都市整備局 都市づくり政策部水資源・建設副産物 担当課長 増井 潔
オンライン現場見学会(シールド工事)
~都心部・長距離・大深度での自然由来汚染土への対応~
株式会社奥村組 千代田幹線工事所
大学生が語る『土の未来 』
<コーディネーター>
東京理科大学 理工学部土木工学科 教授 菊池 喜昭
埼玉大学 大学院理工学研究科 教授 川本 健
<発表者>
東京理科大学 大学院理工学研究科 土木工学専攻 足立 大樹
埼玉大学 工学部環境社会デザイン学科 地盤環境工学研究室 藤崎 鉄心
明治大学 農学部農芸化学科 土壌圏科学研究室 吉田 悠人
早稲田大学 創造理工学部社会環境工学科 地盤工学研究室 鈴木 陽也
東京大学 大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 田島 直樹
~災害と土の先へ~土の未来をさぐる~
<コーディネーター>
公益社団法人土木学会 専務理事 塚田 幸広
<パネリスト>
京都大学名誉教授 嘉門 雅史
事業構想大学院大学 学長 田中 里沙
株式会社 インフラ・ラボ 代表取締役 松永 昭吾
(一社)全国建設発生土リサイクル協会 専務理事 髙野 昇









1968年 京都大学工学部交通土木工学科卒業。 京都大学大学院地球環境学堂学堂長、(独)国立高等専門学校機構 高松工業高等専門学校校長、(独)国立高等専門学校機構香川高等学校校長、日本学術会議会員を経て、2014年(一社)環境地盤工学研究所 理事長・2015年(一財)防災研究協会 理事長・2020 年 (公社)日本工学アカデミー 会長代理・副会長となり、現在に至る。
専門分野は、環境地盤工学、地盤災害、地盤物性、地盤改良。
文部科学省、国土交通省、環境省、経済産業省、京都府、大阪府、香川県、京都市、大阪市、高松市、美馬市、東日本高速道路会社、西日本高速道路会社、阪神高速道路会社、JR東海、その他財団などの研究委員会等の委員長あるいは委員。土木学会、地盤工学会、日本材料学会、防災研究協会など関連学協会の役員や委員会委員長あるいは委員などを務める。

1991年 京都大学大学院工学研究科卒業。 京都大学助手,立命館大学助教授,京都大学助教授,准教授、2009年 京都大学大学院地球環境学堂教授。 国際地盤工学会 2009年~環境地盤工学技術委員会 委員。 2014年~地盤工学会 理事・国際部長。 2014年~2020年 国際ジオシンセティックス学会 理事。 京都大学大学院地球環境学堂・学舎長,現在に至る。
2011年科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)。 2012年日本学術振興会賞。2013年地盤工学会論文賞(英文部門)。

【略歴】
1981年に北海道大学工学部を卒業。建設省入省後、土木研究所研究員、関東地方建設協道路計画第二課長、JICA専門家(フィリピン)、土木研究所施工研究室長、東北地方建設局酒田工事事務所長、国土交通省東北地方整備局企画調整官、建設業課建設業技術企画官、道路局ITS推進室長、近畿地方整備局企画部長、国土技術総合研究所道路研究部長、高度情報化研究センター長、独立行政法人土木研究所研究調整監を経て、2015年より、公益社団法人土木学会専務理事。
【プロフィール】
建設省に入省後、つくばの土木研究所で土工、建設発生土、建設汚泥利用に関する研究・基準・マニュアル化に従事。山形庄内、フィリピンと国内外のフィールドで勤務。国土交通省建設業技術企画官として、建設リサイクル法の周知・運用を担当し、近畿地方整備局企画部長として建設副産物のリサイクルの推進を担当。2021年より(一社)全国建設発生土リサイクル協会顧問、2022年より(一社)道路協会道路土工委員長を努める。最近の主張:「土は自然・脱炭素等環境にやさしく、素晴らしい資源。技術を革新し、土工構造物への関心を高めるべき」

広報・広告・マーケティングの専門誌「宣伝会議」編集長、取締役編集室長を経て、2016年より地方創生と新規事業の研究と人材育成を行う、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学学長。企業や自治体、他大学との連携による共創、イノベーション、地域デザインのプロジェクト等を企画し、推進する。「クールビス」ネーミング、東京2020エンブレム、大阪・関西万博キャラクター審査員。社会資本整備審議会、地方制度調査会、中央環境審議会、財政制度等審議会、ナショナル・レジリエンス懇談会、土木広報大賞等の委員を務める。

橋の設計・維持管理、地震・噴火・豪雨災害等の災害調査・復旧計画を専門とする土木技術者。大学、高専、行政機関等において講師をつとめるかたわら、舟遊びガイド(東京)や、噂の土木応援チームデミーとマツとして子どもたちに土木工事の本物体験イベントを開催している。土木広報大賞3回連続受賞。モットーは「土木は優しさをかたちにする仕事」。
博士(工学)、技術士(総合技術監理、鋼構造及びコンクリート、道路)、土木学会上級土木技術者、防災士。土木学会地震工学委員会委員、WEB版土木広報誌fromDOBOKU編集長、土木図書館委員、日本建築学会員。土木学会「未来の土木コンテスト2022」選考委員長。 (株)サザンテック執行役員上席技師長。趣味は土木写真と歴史散歩、読書。1970年長崎県佐世保市生まれ。

1996年 東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 博士前期課程 修了
1997年 埼玉大学大学院 理工学研究科 助手
2002年 東京大学大学院 農学生命科学研究科 博士号
2007年 埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授
2013年 埼玉大学大学院 理工学研究科 教授(現職)
2005年~2006年 オルボー大学(デンマーク)客員研究助手
2009年 フィリピン大学ディリマン校土木学科 客員教授
2009年 東ティモール大学土木学科 国際協力機構(JICA)短期派遣専門家
2011年~2016年 JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事業 「スリランカ廃棄物処分場における地域特性を活かした汚染防止と修復技術の構築」 JICA専門家(主研究取組者)
2018年~ JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事業 「ベトナムにおける建設廃棄物の適正管理と建廃リサイクル資材を活用した環境浄化および及びインフラ整備技術の開発」 JICA専門家(研究代表)
2019年~ ハノイ国立建設大学 客員教授
専門は地盤環境工学、廃棄物資源循環工学、土壌科学

1983年 東京大学大学院工学研究科修了。同年 運輸省採用。
港湾技術研究所研究官、主任研究官、独立行政法人港湾空港技術研究所 基礎工研究室長、地盤構造部長、特別研究官を経て、2012年東京理科大学理工学部土木工学科教授。現在に至る。
国土交通省の港湾関係の委員会の委員、委員長を多数務める。
所属学会:地盤工学会、土木学会、国際ジオシンセティックス学会、国際圧入学会。
専門は地盤工学、杭基礎、地盤環境工学。

【略歴等】
1977年3月東京教育大学理学部地学科(陸水学)卒。
2018年3月放送大学大学院文化科学研究科社会経営科学プログラム修士課程修了。
1977年4月CRC(現、CTC)。
1982年9月日本能率協会総合研究所(JMAR)。
2015年7月ACTEC、2021年4月よりJASRA 非常勤理事を兼務。
技術士(総合技術監理、建設、衛生工学)、土木学会フェロー、土木学会認定特別上級技術者(環境)
【業務実績等】
CRCでは環境アセスメント(大気、水質、地下水)業務に従事。
1982年JMAR入社後、国、自治体の残土(建設発生土)、建設リサイクル関係調査に従事。
担当した主な施策等:建設リサイクル法、建設リサイクル推進計画、建設副産物実態調査、建設発生土情報交換システム(基本設計)、東京都建設残土対策基本方針・建設発生土再利用センター(基本計画)、㈱首都圏建設資源高度化センター(現、建設資源広域利用センター、設立準備)
「オフィシャルスポンサー」とは、会場内のPRブースをご利用いただける企業様、並びにブースの利用なしに、土サミットのコンセプト全体に賛同いただいている企業です。

株式会社泉興業
協賛コメント
大坪GSI株式会社
協賛コメント
株式会社奥村組
協賛コメント
兼松エンジニアリング
株式会社

株式会社環境施設
協賛コメント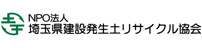
NPO法人埼玉県建設発生土リサイクル協会
協賛コメント
株式会社サンエコセンター
協賛コメント
ジャイワット株式会社
協賛コメント
株式会社田中建設
協賛コメント
株式会社谷田建設
協賛コメント
株式会社張本創研
協賛コメント
株式会社ホツマプラント
協賛コメント
株式会社吉光組
協賛コメント
株式会社Lien du coeur
協賛コメント※50音順
「オフィシャルサポーター」とは、土サミットに協賛し応援いただいている企業様です。

イズミ環境サービス
株式会社
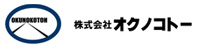
株式会社オクノコトー

下越物産株式会社

株式会社カガ三
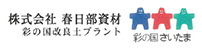
株式会社春日部資材

有限会社光南台土建

コマツカスタマーサポート株式会社

五葉建材株式会社
エコプラザ さいたま
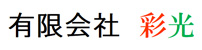
有限会社彩光

株式会社栄自動車工業

有限会社鷺斫り

株式会社 シー・エス・エム

株式会社JRS

昭和鋼機株式会社

株式会社
スカイクリーンツヤマ

鷹取建材株式会社
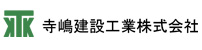
寺嶋建設工業株式会社

株式会社トライテク
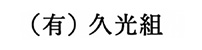
有限会社久光組

株式会社フジモト
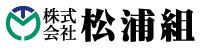
株式会社松浦組

株式会社丸本建設

有限会社ワコー産業
※50音順
一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会では、活動の趣旨についてご賛同いただける企業・団体の皆さまを対象に「土サミット2022 TOKYO」のオフィシャルスポンサーとサポーターを募集いたします。皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
別紙「協賛申込書」Wordファイル版に必要事項を記入し、バナー広告用データを添付のうえ、電子メール「info@tsuchi-summit.com」(pdfファイル可)によりお申し込みください。


株式会社泉興業は、特殊車両を使用し泥水等の収集運搬・清掃業を中心に、各プラントメンテナンス・土木工事による現地改良工を行っております。
循環型社会と低炭素社会への実現に向けた取り組みが求められる現在、環境事業を通じ、限りある資源を大切にし、未来を担う次世代に、よりよい環境を引き継げるよう。資源循環型社会の形成に向け努めております。
命を育てる「土」について、広い分野でのネットワークが広がることを願っております。


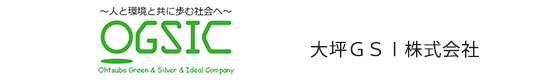
土サミット 2022 TOKYO が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
大坪GSI株式会社の社名につくGSIの G は「グリーン(環境)」、S は「シルバー(高齢化)」、 Iは「 アイデアル(理想的な)」の略です。
ここには、グリーン(環境)とシルバー(少子高齢化)をキーワードに、理想的な社会の構築に貢献できる会社であり続けたいという思いが込められています。
大坪GSI株式会社では、皆さんに寄り添ってお困りごとを解決していく。
より地域に根ざした活動をすることで皆さんから本当に喜ばれる存在、愛される存在になりたいと願っています。
大坪GSIの周りには社員、お客様、仕入先、協力業者、地域社会などさまざまな方がいます。今後も当社に関わる全ての方々が幸せになれるような会社づくりに取り組んでまいります。



奥村組は、1907年に創業し、堅実経営・誠実施工を信条に、土木・建築事業等を展開する総合建設会社です。
免震をはじめとする防災関連技術や省エネ技術に強みを持ち、既存建物の有効活用、リサイクルやリニューアル、汚染土壌対策等の環境保全技術の開発、さらには災害対応にも積極的に取り組んでいます。
今回、「土サミット2022TOKYO」の開催に向け、ご協力させていただく機会を頂戴いたしましたことを、大変ありがたく存じます。
激甚化している近年の災害に対し、「災害と土」「土の未来」というテーマによるご講演やディスカッションを通じて、「土」が持つ本来の役割・将来性を広く発信することに少しでも貢献できれば幸いです。



「課題を吸いあげ、未来を引き出す」
創業1971年、兼松エンジニアリングが磨きつづけてきたのは吸引技術だけではありません。
お客様や社会の抱える課題を見いだし、吸いあげ、解決策を引きだす力・・・
いわば、よりよい未来を生み出すための「吸引力」こそ、私たちが培ってきた最大の強みです。
人を、環境を、地域を思い、そこから引き出される次なる未来にぜひご期待ください。
今回、土サミット 2022 TOKYO が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。



土サミット 2022 TOKYO が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
株式会社環境施設は「新しい時代を創造する」ことを使命とし、自然との対話を大切にしています。人のため、地域のため、地球のために私達の快適な生活環境を創るため循環型社会の向上を進めています。

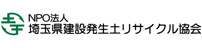
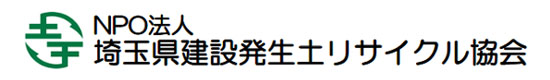
土サミット 2022TOKYO 開催を心よりお慶び申し上げます。
当協会は、平成9年に任意団体として発足し、平成18年10月には認定プラントを持つ正会員と当協会の目的に賛同される賛助会員で構成される、特定非営利活動法人として、発足より現在まで25年間にわたり活動を続けております。
これまで、建設発生土のリサイクルを普及推進し、地球環境保全に貢献することを基本方針として、改良土の利用を推進することにより地球温暖化防止、循環型社会の構築を目的として活動しておりますが、今後は建設発生土のリサイクル率向上を更に図り、最終処分場に頼らない持続可能な社会構築を目指してまいります。



「土サミット2022」を応援します!
株式会社サンエコセンターは、埼玉県のなかでいち早く建設発生土のリサイクル事業に取り組んで参りました。
「土」という資源を無駄なく再利用することで、環境保全を推進し持続可能な社会の実現を目指して参ります。



ジャイワット株式会社は土のリサイクルを目指した企業です。千葉支店では製紙汚泥焼却灰を主原料とした吸水性泥土改質材「ワトル」の製造販売、仙台支店では建設汚泥のリサイクルを行っております。
この度の「土サミット2022」を通して土リサイクルの普及に貢献できればと願っております。


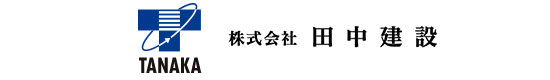
物語は未来の地球へ。
私たち株式会社 田中建設のストーリーは、土のリサイクルシステムをはじめとした環境保全・循環型社会の構築。
これらを明日の地球に残すプロフェッショナル集団として社会に貢献してまいります。



株式会社谷田建設は、「捨てるから創るへ」をキャッチコピーで美しい地球と将来の子供達の環境を守る為に、再資源化に力を入れております。
この「土サミット2022TOKYO」を通して、「土」を安心して再利用できるように努めてます。



株式会社 張本創研は、「限りある資源を次世代へ」をテーマとして循環型社会形成を推進し、もったいないをスローガンとして掲げ地球資源を大切にし、再資源化に努めております。
地球の資源である「土」を未来のために活かしましょう。



株式会社ホツマプラントは、「土」のリサイクルを通し、環境負荷低減をはかり、次の世代へ緑豊かな大地を残す事業を行っております。
ホツマプラントの社名は、環境破壊がなく自然の流れと共に生きていた、いにしえの昔・秀真(ホツマ)の国の頃に想いを馳せ、環境問題に取り組むという深い思いからきております。
土サミットを通して多くの「土」の情報が皆様に伝わり、新しい未来が開けてゆく事を願っております。



土の持続可能な開発を目指して
株式会社吉光組は、大正2年より土木・建築事業を行う総合建設会社です。
近年では工事から排出される土のリサイクルシステムを構築し、道路や河川、空港に鉄道と幅広く社会インフラに利用されるようになりました。
「土サミット2022TOKYO」を通じて、社会が土を見つめ直す機会となる事を願っております。


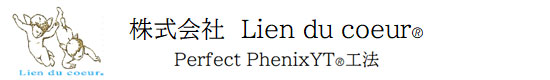
株式会社Lien du coeur(リアン ドゥ クール)は重金属汚染土の無害化処理に取組んでいます。
弊社パーフェクトフェニックスYT工法は、2021年にNETS登録され、2022年4月国土交通省岐阜国道事務所承認による実証試験施工を行いました。
同工法は重金属汚染土を化学反応により難溶性化合物にし二次反応により二重結合させ不溶性化合物として永続的に解離させない世界初の汚染土壌改質工法です。
特殊改良した攪拌機により攪拌効率を30%向上させ安全第一に考えた工法です。
更に不溶改質された資源はリサイクル品として有効活用される環境に優しい循環型工法となります。
今回「土サミット2022TOKYO」に御協力させて頂く機会をいただけました事、幸甚に存じます。
「土」の力を再大限引き出し社会に貢献できればと願っております。

東京都千代田区紀尾井町4-1
詳しいご案内はホテルニューオータニ東京公式サイトをご覧ください。
※土サミットへの参加は事前登録が必要です。
受付は終了いたしました。
ホテルニューオータニ東京
〒102-8575 東京都千代田区紀尾井町4-1